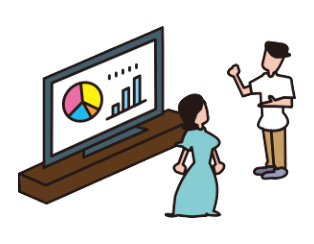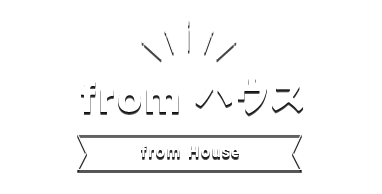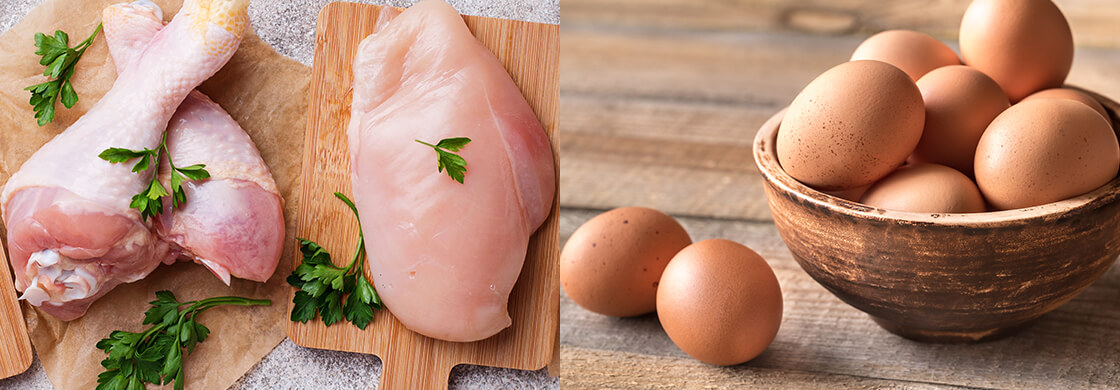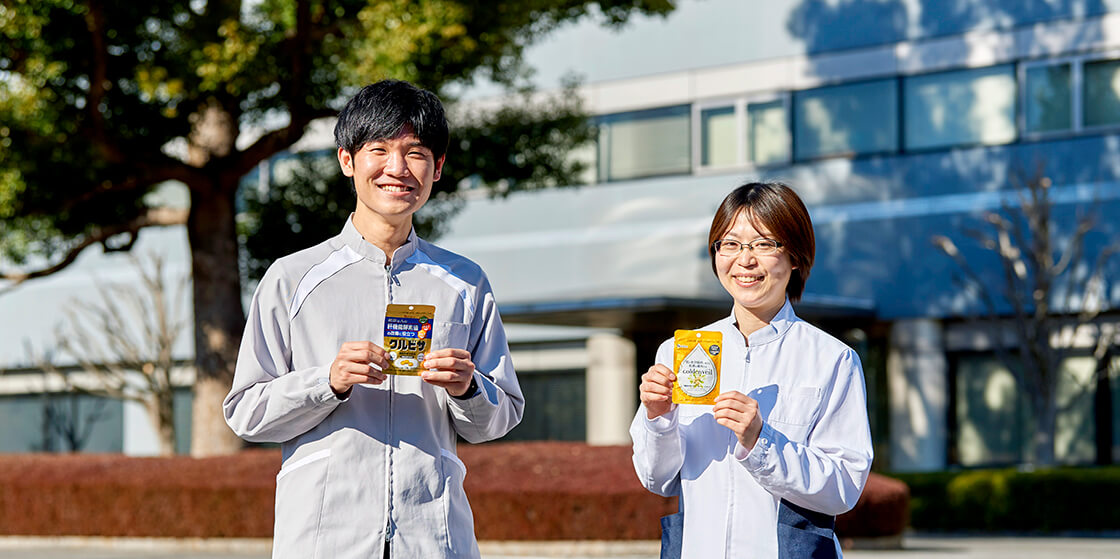もうすぐクリスマス。定番料理の一つでもある「ローストチキン」を楽しまれる方も多いのではないでしょうか。そこで、今回は“鶏肉”がクリスマスに食べられるようになった理由から、子にあたる“卵”についても各部位の栄養素や、おいしく賢く食べられるおすすめメニューをご紹介します。
“鶏肉”や“卵”は、たんぱく質が豊富なことでも知られている代表食材ですが、ほかにもからだづくりに大切な栄養がたくさん含まれています。
“鶏肉”と“卵”の特徴や違いを知って、日頃のからだづくりに役立ててみてくださいね♪
クリスマスにローストチキン(鶏肉)を食べるのはなぜ?

12月25日のクリスマスはイエスキリストの誕生日。キリスト教信仰者の多い欧米では、この12月25日や前日の12月24日(聖夜)を豪華な食事で祝い、中世ヨーロッパでは豚や羊を食べて感謝の意を表していたそうです。その後、ヨーロッパからアメリカに渡った開拓民が食料の調達に苦労していたところに、先住民から七面鳥の施しを受けたことから、ローストターキーをシェアして食べる習慣がはじまったといわれています。
1匹まるごとローストすると大勢で分け合え、お腹を満たせることがイエスキリストの教えとも重なり、聖夜を祝う料理としてふさわしかったのでしょう。今ではローストターキーのほかにもローストビーフやハムなど、同じようにみんなで切り分けて食べるご馳走がクリスマス料理として定着しています。
日本では、明治以降にクリスマスを祝う文化が普及。しかしアメリカとは違い、七面鳥は入手が困難だったことや、日本の台所事情では大きすぎてローストしにくいなどの理由から、手ごろで調理しやすい“鶏肉”をローストして食べる習慣が広まりました。
“鶏肉”と“卵”は親子だけど栄養素は違う?!
“鶏肉”と“卵”には、からだづくりに欠かせない栄養素がたくさん含まれています。それぞれに含まれる栄養素や特に多く含まれる部位などをご紹介します。
<“鶏肉”と“卵”の両方に含まれる栄養素>
- ●たんぱく質
肌や筋肉、髪、爪など、からだをつくる大切な栄養素です。ささみや、むね肉は特に多く含まれます。
- ●ビタミンB2
皮膚や粘膜の健康を保つので、冬の乾燥する季節には積極的に摂ると良い栄養素です。
<“鶏肉”に含まれる栄養素>
- ●ビタミンK
ビタミンのなかでも油に溶けやすい脂溶性ビタミンで、止血(血液凝固)や骨の健康を維持する効果を持ちます。特に皮つきの“鶏肉”に多く含まれます。
- ●ビタミンB6
からだをつくるたんぱく質の代謝を助ける働きがあります。ささみ、むね肉に豊富に含まれます。
- ●亜鉛
味覚を正常に保ち、たんぱく質の代謝にも関わります。日本人に不足しがちなミネラルを効率よく摂るには、もも肉と手羽先がおすすめです。
- ●パントテン酸
善玉コレステロールを増やすほか、ホルモンや抗体の合成や生成にも関わっています。
- ●イミダペプチド
むね肉に含まれるイミダペプチドは疲労を回復させ、脳の老化改善にも効果があるとされています。
<“卵”に含まれる栄養素>
- ●ビタミンA
目や皮膚の粘膜を健康に保ったり、抵抗力を強めたりする働きがあるビタミンです。
- ●ビタミンD
カルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助けるので、成長期だけでなく、すべての世代で積極的に摂りたいビタミンです。
- ●ビタミンE
抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。
- ●コリン
脳の働きを活性化し、認知機能維持に効果があるといわれています。
“鶏肉”と“卵”のおいしい食べ方
“鶏肉”の部位や“卵”の黄身と白身は、それぞれの特質を生かした用途や料理方法があります。ここでは、おいしく食べられる「おすすめメニュー」を紹介しましょう。
<“鶏肉”の部位別おすすめメニュー>
- ●もも肉
脂質が適度にありジューシーなもも肉は、から揚げ・焼鳥・ソテー・煮込み料理・スープなど幅広い料理で活躍してくれます。
- ●むね肉
脂質が少なくあっさりしているむね肉は、加熱しすぎるとパサつきやすいので気をつけましょう。塩麹や味噌などと合わせるとお肉が柔らかくなり、おいしく仕上げることができます。おすすめメニューには、野菜と一緒に食べる蒸し鶏やサラダチキンのほか、子どもにも大人にも人気のから揚げなどが挙げられます。
- ●ささみ
脂質が少なくてパサつく印象のあるささみですが、お酒をふって加熱することでジューシーに仕上げることができます。カツや蒸し鶏、ほぐしてサラダのトッピングにするのもおすすめです。
- ●手羽先(手羽元)
脂質があり、うま味もたっぷりでジューシーな手羽先。出汁がよく出るので、煮込んでスープをつくるのもよいでしょう。から揚げ・スープ・焼き物・煮物など、幅広くご利用いただけます。
<“卵”の使い分けおすすめメニュー>
- ●全卵
バランスのよい味わいで、ゆで卵や卵焼き・ケーキのスポンジなど、幅広いメニューに使うことができます。
- ●卵黄
コクがあるので、カスタードクリームやカルボナーラがおすすめ。お肉や魚の照り焼き丼などにのせて食べると味がマイルドになります。
- ●卵白
起泡性が高いので、しっかり泡立てて使うと、ふわふわのオムレツやパンケーキをつくることができます。エビにしっかりもみ込んで調理するとプリプリの食感になったり、スープに入れたりしてもおいしく味わえます。
卵黄はビタミンAやビタミンB群・ビタミンDが多く含まれ、卵白は低脂質で高たんぱく。“卵”の大きさが変わっても卵黄の大きさはほぼ同じで、卵白の重さが異なることも、豆知識として覚えておきましょう。
組み合わせ次第で栄養アップ!効率よく食べる方法は?
 “鶏肉”と“卵”の栄養素を上手に組み合わせて食べることで、バランスよく、効率よく栄養を摂ることができます。
“鶏肉”と“卵”の栄養素を上手に組み合わせて食べることで、バランスよく、効率よく栄養を摂ることができます。
たとえば、手羽先や手羽元にはコラーゲンがいっぱい含まれているので、コラーゲンの吸収を助けてくれるビタミンCが豊富なイモ類と一緒に料理すると、効率よくコラーゲンを摂取することができます。
“鶏肉”に含まれるビタミンKは、カルシウムと一緒に摂ると効率がよいので、“鶏肉”のクリーム煮は優秀な組み合わせです。
“卵”は、ビタミンCと食物繊維が多いサツマイモを使ったポテトサラダにしたり、きのこ(食物繊維)とピーマン(ビタミンC)のオムレツなどにすると、効率よく栄養素を補うことができます。
また、運動後はたんぱく質の摂取に効果的です。からだが積極的にエネルギーを回復しようとするため、運動後およそ30分から1時間を目安にたんぱく質を摂取するとよいでしょう。スポーツをする方は、ゆで卵などを持ち運びやすいものを用意するのもおすすめです。
いかがでしたか?普段の食卓でも馴染み深い“鶏肉”と“卵”ですが、部位を使い分けたり、組み合わせを工夫したり、ご紹介した内容を参考に、上手にメニューに取り入れてみてくださいね。
-

プロフィール
野口 知恵(のぐち ちえ)
管理栄養士、野菜ソムリエ上級プロ
和食文化継承リーダー(農林水産省)、食育仕事人(近畿農政局)
大学では食物栄養学部卒、大手食品メーカーで企業へのメニュー提案や商品企画を経て、独立後は講演やレシピ開発、執筆、メディア出演などを通じて「野菜・果物× 健康×栄養=笑顔」を伝えている。